小3らくらく授業開き【モトヨシ先生のスライドde外国語活動】
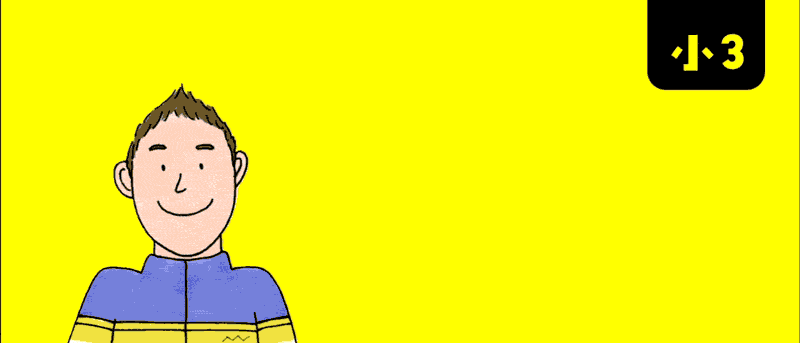
ゆたかな言語活動を行うためにICTを活用した授業が求められる外国語活動。しかし、様々なツールや教材を切り替えながらでは、手惑う場面もしばしばでしょう。本好利彰先生がこれまでの授業で作成してきたパワーポイント(スライド)教材は、これひとつ、授業の導入から終末までモニターに映すだけで授業を組み立てられる”お助け教材”です。「モトヨシ先生のスライドde外国語活動」で外国語活動の授業を、らくらくクオリティアップ!
執筆/千葉県公立小学校教諭・本好利彰
監修/拓殖大学准教授・居村啓子
目次
楽しいと感じる授業開きを!
小学校3年生の「Let’s Try!1」の授業に入る前の授業開きの1時間の流れです。外国語活動を初めて学習する児童に外国語活動は楽しいと感じてもらえるような簡単な活動をいくつか準備し、1時間の構成を考えてみました。学級の実態に合わせてパワーポイント(スライド)を修正して活用してもらえればと思います。授業の終末には外国語活動の授業のルールを確認するとよいでしょう。
パワーポイント(スライド)を使った授業の進め方
この記事の最後で、パワーポイントのファイルをダウンロードできるようになっています。必要な教師の発話やイラスト、音源などを挿入してあり、この資料を使うことで1時間の授業を行うことができるように作成してあります。このスライドを活用して、クリックしながら授業を進めてみてください。![]()
- クリックでスライドを進めるだけで、スムーズに授業を行えます。
- デジタル教科書を使用する場合は、パワーポイントから切り替えてください。
目標と授業の流れ
【目標】
動作や数字の英語に慣れ親しもう。
【言語材料】
◎stand up, sit down, touch your headなどの動作を表す単語
◎数字(1~12)
◎挨拶(hello, see you)
- あいさつ
- 動作の英語表現に慣れる
- サイモンセズ
- めあての確認
- 数字の練習(1~12)
- What’s missing?
- 記憶力ナンバーゲーム
- 歌を歌う
- イレイサーゲーム
・時間があれば爆弾ゲーム、パチパチ3 - 授業のルール&ふりかえり

