道徳は、自分の価値観の変化を自分の言葉で語り合うこと
愛知淑徳大学非常勤講師・柴田八重子さんは、著書『みんなで創ろう!主体的・対話的で深い学びのある道徳科の授業』の中で、「対話」と「中心発問」の重要性を説かれています。「中心発問の重層化」についての具体的なステップを紹介いただくともに、授業を通してのゴールはどこに設定すべきなのか、詳しくお話を伺いました。
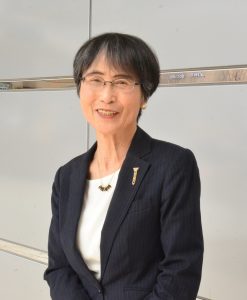
愛知淑徳大学非常勤講師
柴田八重子さん
目次
授業の基本は中心発問創り
――著書では、「特別の教科道徳」 において「主体的・対話的で深い学び」を目指すとき、なぜ、「対話」や 「中心発問の重層化」にこだわるのかについて解説されています。
柴田 私は、道徳科の授業の基本は、 中心発問創りだと思っています。「ねらい」とする価値項目に対する今までの自分の価値観を改めて知り、級友の力を借り、自分の価値観の新たな高まりを実感する――。子どもたちとともに、すべてをそこに向けます。
中心発問では最初、教材世界の言葉を使い、率直な考え・思いを語り合います。語りながら、自分の価値観に気付き始めます。
「中心発問の重層化」とは
――「中心発問の重層化」とはどのようなことでしょうか。
柴田 一層目の段階では「こういうことだな」「言葉にできるぞ」と思えたら、そっと立ち上がります。クラス全員が立てたら、誰かから発言をし始めます。よく聞いていて、自分も内容が同じだと思ったら、発言者と一緒に座ります。全員座るまで聴き合い、クラス全体でどういう意見が何種類出ているか確認し、議論の準備をします。
自分の位置、みんなの位置がわかったところで、次の段階に入ります。
A〜Eまでの5種類の意見が出たら、なぜその意見に至ったのか、根拠と理由を言う二層目に入ります。
始めは教材内の状況言葉で「そうか!」「いやそれは許せん!」等の意見が出てきます。教材内の議論です。そのうち、教材内言葉が自分言葉になり「わかっているけど、でも ……。」「私たちってほんとに○○の大事さがわかっているかなあ?」と価値観が出てき始め、「○○ってこと、俺は難しいよ」と人間の弱さとみんなで真向かいし、○○の難しさと意義が対話で深められ、◎◎が見えてきます。
授業の3層目までいくと、自分の変化成長が言えるようになります。「俺、嫌になってきた。今まで浅はかだった。A君の意見を聞いて、ああ、そうかと思った」という振り返り感想を出してくれます。「今すぐこうしますとは言えないけど、Bさんの意見を聞いて、自分が恥ずかしくなった」など、価値観がどう変化 してきたかを自分の言葉、次元で言います。お互い励まし合いながら。


