小2算数「長さ」指導アイデア《自分の足の大きさを測ってみよう》
執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・黒木正人
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥
目次
本時のねらいと評価規準
(本時2/9時)
ねらい
自分の足の大きさを測る活動を通して、無意識に使っていた「センチメートル」という言葉の意味を理解する。
評価規準
形の特徴に着目し、どこを長さと規定するか考えて測定することができる。

問題
自分の足の長さはどのくらいでしょう。
*子供がそれぞれ長さを言う。
上履きのサイズを見たら、みんな分かるよ。
上履きのサイズと足の長さは同じですか。
上履きよりは小さいと思います。
長さを知りたい。
測ってみたい。
では、自分の足を測ってみましょう。
足の長さってどこのことだろう。
横ではなさそうだから、縦かな。
上履きの縦の長さがサイズになっていると思います。
足の長さも縦の長さを測ったらよいと思います。
足の縦の長さを測るということでよいですか。
はい。
でも足は丸くて、まっすぐじゃないから測りにくいな。
くつ下を脱いだら測りやすいと思います。
ものさしで測ればまっすぐになるよ。
つま先とかかとをまっすぐに測ればよいと思います。
足の縦の長さがどこからどこまでなのかを決めて、その測り方を考えてみましょう。
学習のねらい
どこからどこまでが長さなのかきめて、はかり方を考えよう。
見通し
ものさしに足を当てたらできると思うよ。
線を引くと測るところが分かりやすくなるはず。
自力解決の様子
A つまずいている子
長さとする部分が見いだせず、測ることができない。
B 素朴に解いている子
足を持ち上げて、ものさしを足の裏に当てて測っている。
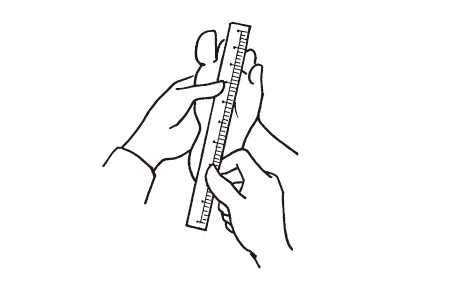
C ねらい通りに解いている子
足の形を紙に写して、両端の2点を決め、測っている。
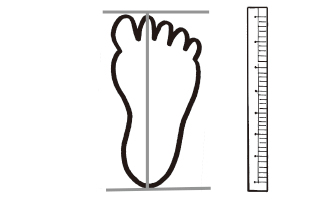
学び合いの計画
子供は量の大小判断を、日常生活のなかで無自覚的に行ってきています。測定の活動では、無自覚的に行っていたことを、自覚してできるようにすることが大切です。一年生では、アサガオの茎の長さのように一見測りにくいものを、紙テープなどを用いて間接的に測ることを経験しています。
イラスト/松島りつこ・横井智美
『教育技術 小一小二』2021年4/5月号より

