小6道徳「星野君の二塁打」徳目に反する事実を提示する
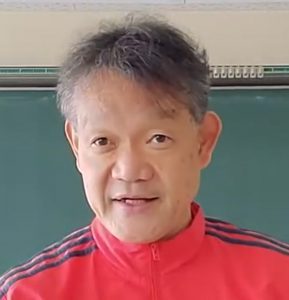

執筆/奈良県公立小学校・土作彰
教材名:「星野君の二塁打」(学校図書 道徳「かがやけみらい 6年」)
内容項目:約束と規則の尊重 [4-(1)]
目次
教材「星野君の二塁打」について
定番の道徳教材です。以前、「道徳の教科化」を取り上げたテレビ番組でも、道徳教育研究校の公開授業の教材として取り上げられていました。
この教材の価値項目は「規則の遵守」です。簡単に要約すると、次のような話です。
星野君は少年野球チームの選手。ある公式戦でのチャンスに星野君に打順が回ってくる。ここで監督が出したのは、バントのサインであった。しかし、この日、星野君は打てそうな予感がして反射的にバットを振り、結果二塁打を放つ。この二塁打でチームは勝利し、チームは選手権大会出場を決めた。
だが翌日、監督は選手を集めて重々しい口調で語り始める。チームの作戦として決めたことは絶対に守ってほしい、という監督と選手間の約束を持ち出し、みんなの前で星野君の行動を咎める。
『いくら結果がよかったからといって、約束を破ったことには変わりはないんだ』『犠牲の精神の分からない人間は、社会へ出たって、社会をよくすることなんか、とてもできないんだよ』などと語り、次の試合に先発出場させないことを宣告する。
この教材に対する批判は数々なされています。「野球を知らない子には、この状況は分かりにくい」「野球チームという限られた組織内での規則を、一般社会での規則と同一視するのはどうか」などのようにである。
しかし、この教材に対して批判をするだけではあまりに能がありません。この道徳の教科書の教材に正対し、子供たちに考え、議論させる授業を構想します。
授業進行の原動力は矛盾
従来の道徳授業では、子供が教師の意図を見抜き、教師の求める答えを述べたり書いたりして終わるという、白々しい授業展開が問題とされています。この「星野君の二塁打」も教科書の流れでいけば、「規則は個人の恣意によって破られるべきではない」という結論になることは、容易に推測できます。
このような内容でどうやって子供たちに考え、議論させるというのでしょう? ここで紹介するのが小見出しにある「授業進行の原動力は矛盾」という言葉であり、次のような見解があるのです。
「授業進行の原動力は、授業の中で生まれる様々な矛盾であり、最も基本的な矛盾は、授業の中で子供たちに対して提起される新しい課題と、その課題を解決するために、子供が持っている前提条件との間の矛盾である」
(吉本均編『教授学重要用語300の基礎知識』)
教材の中に何の矛盾点もなければ、子供たちは思考停止のまま、差し障りのない感想を書いて授業を終えることになります。そこで、子供たちに「矛盾」を感じさせる授業展開にする必要があります。
このような授業構造を持った授業と言えば、群馬県の元小学校教師・深澤久氏の提唱した「命の授業」が挙げられます。簡単に言えば、次のような構造になっています。
①既知の徳目を確認し、強化する資料を提示する。
②その徳目に反する事実を含んだ資料を提示する。
この構造により、子供たちは「矛盾」を感じることになり、思考を活性化させることができるのです(ただし、活発な議論になるかどうかについて、深澤氏は「それまでの学級経営が反映される」と述べています。深澤久『命の授業~道徳授業の改革をめざして~』P98)。

