小3理科「こん虫をそだてよう」指導アイデア
執筆/福岡県公立小学校教諭・寺川智紀
編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・藤井創一
目次
単元のねらい
子供が、身の回りの生物について、探したり育てたりするなかで、それらの様子や周辺の環境、成長の過程や体のつくりに着目して、それらを比較しながら、生物と環境とのかかわり、昆虫の成長のきまりや体のつくりを調べる活動をしていきます。それらについての理解を図り、観察・実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成することが目標です。

単元の流れ(四次 総時数10時間)
一次 チョウの育ち方(5時間)
①卵を観察し、飼育の準備する
②卵の変化の様子を観察する
③幼虫の育つ様子を観察する
④さなぎの変化の様子を観察する
⑤成長のきまりについてまとめる
身近な生き物である「チョウ」の飼育を行うことで、昆虫の成長する様子や体のつくりへの興味・関心を高めます。その後、ほかの昆虫の成長の様子や体のつくりについて、共通点や差異点を見いだしながらまとめていくことで、身の回りの生物についての理解を深めることができるようにします。
二次 チョウの体のつくり(1時間)
①チョウの体のつくりを観察する
三次 トンボやバッタの育ち方(2時間)
①幼虫を飼って、育ち方を調べる
②チョウの育ち方と比べる
見方 主として「共通性・多様性」
<共通性>
・昆虫の主な育ち方は、「卵→幼虫→成虫」である。
・昆虫の体のつくりは、頭・むね・はらの3つの部分からできていて、むねには6本の足が付いている。
<多様性>
・「卵→幼虫→さなぎ→成虫」の育ち方・・・完全変態
・「卵→幼虫→成虫」の育ち方・・・不完全変態
考え方
チョウとトンボやバッタの成長の様子、体のつくりの特徴を「比較して」考える。
四次 トンボやバッタの体のつくり調べ(2時間)
①トンボやバッタの体のつくりについて調べる
単元の導入はこうしよう!
キャベツの苗を植えておこう(生活科との連携)
5月ごろになると、育てているキャベツにモンシロチョウが寄ってきます。その機会を捉えて「花が咲いていないのに何をしているのかな」という子供の疑問を取り上げることで、モンシロチョウの産卵や卵に気付き、単元の導入をスムーズに行うことができます。

予想を大切にしよう
子供たちは生き物の成長や体のつくりについて、不確かなイメージしかもっていません。単元導入時に、モンシロチョウの成長の様子や体のつくりについて、今までの生活体験を根拠に予想をもたせておくと、観察の視点が明確になり、新たな気付きや発見を得ることができます。
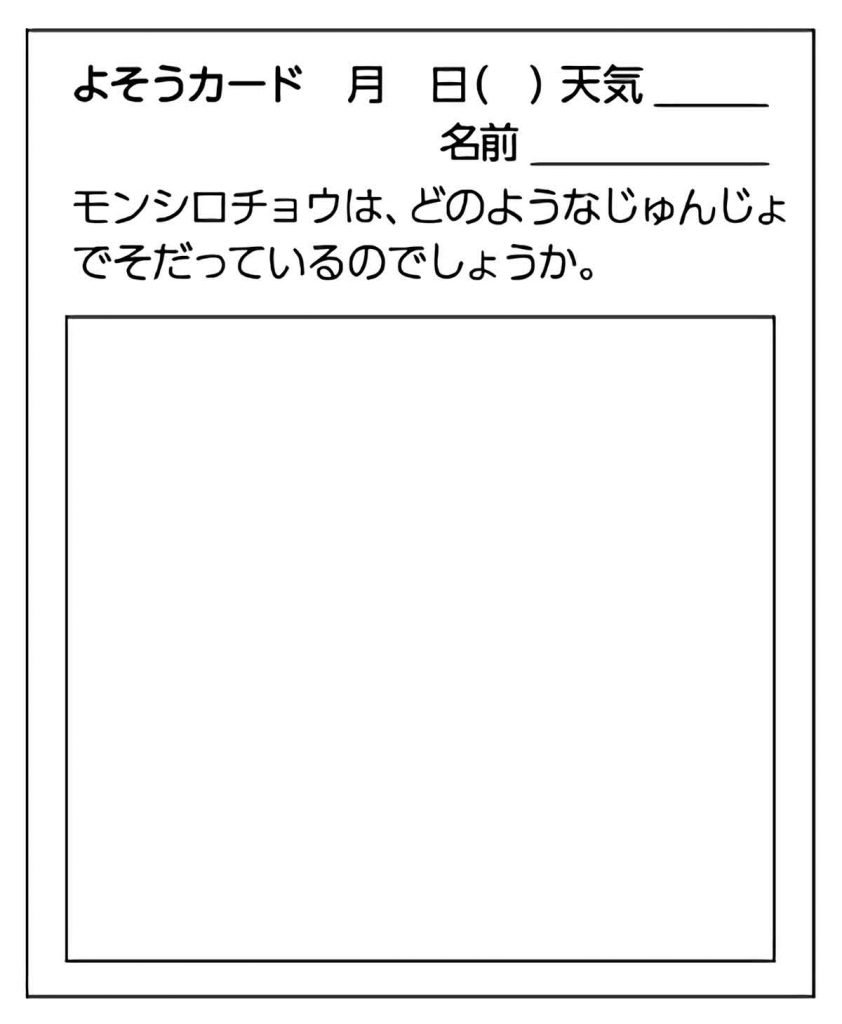
活動アイディア 資質・能力の育成をめざして!
モンシロチョウの体のつくりと比較しながら、トンボやバッタの体のつくりを観察します。モンシロチョウと比較しながら追究することで、モンシロチョウとトンボやバッタの体のつくりの共通点(昆虫の特徴)に気付き、問題解決の力の育成につながります。
授業の展開例 (第四次 第1時)
イラスト/たなかあさこ
『教育技術 小三小四』2019年6月号より

