小1生活「なつが やって きた」指導アイデア
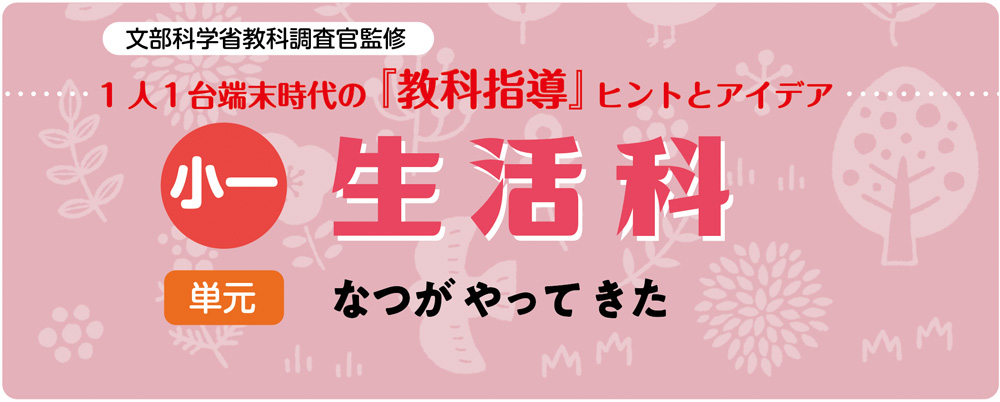
文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「なつが やって きた」の単元を扱います。
執筆/高知県公立小学校教諭・都築万季
編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸
高知県公立小学校校長・尾中映里
目次
年間指導計画
年間指導計画(クリックすると表示します)
| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |
| 5月 | がっこう だいすき |
| 6月 | きれいに さいてね |
| 7月 | なつが やって きた |
| 8月 | いきものと なかよし |
| 9月 | あきを さがぞう |
| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |
| 11月 | あきまつりを しよう |
| 12月 | じぶんで できるよ |
| 1月 | ふゆを たのしもう |
| 2月 | しん1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |
| 3月 | もうすぐ 2ねんせい |
単元目標
夏の自然と関わったり、それを利用して遊んだりする活動を通して、身近な自然の違いや特徴を見付けたり、遊びや遊びに使う物を工夫して作ったりすることができ、身近な自然の様子が変わることや、自然を使った遊びの面白さに気付くとともに、身近な自然を取り入れて自分の生活を楽しくしようとしたり、みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとしたりすることができるようにする。

