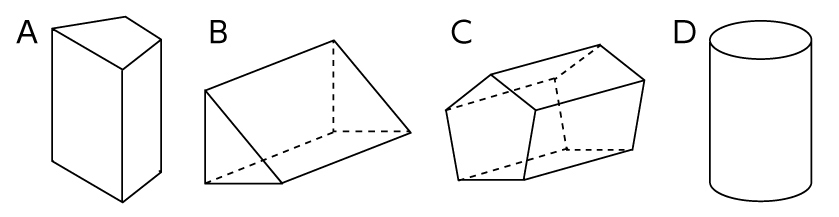小5算数「角柱と円柱」指導アイデア《底面の形に着目して立体の特徴を理解しよう》
執筆/新潟県公立小学校教諭・樋浦教之
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟県公立小学校校長・間嶋哲
目次
本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/7時)
ねらい
角柱や円柱について、立体2ヒントクイズの質問を修正する活動を通して、底面に着目することで立体の分類が可能となることを理解できる。
評価規準
底面の形に着目して、六角柱の2ヒントクイズを考えることができる。
みんなで立体2ヒントクイズをしましょう。
立体2ヒントクイズ
①この立体は、転がり( )。
②底の形は( )。
【立体2ヒントクイズのルール】
①先生から、ヒントが1つずつ出される。
②( )の中にヒントの言葉が入る。
③分かったら、その図形の番号を答える。
④ヒントは、2回まで。
第1問。ヒントを1つずつ言います。
①この図形は、転がり(ます)。
それぞれの立体を置く向きを、上の絵のように提示しておきます。
分かりました! 簡単です! 最初のヒントだけで分かったよ!
答えは、Dです。周りの面が曲がっているから、転がります。
正解です。Dの形を「円柱」といいます。周りの面は「曲面」といいます。A~Cには、曲面はありませんね。
第1問の正解を確認した後、「円柱」「曲面」という言葉を知らせる。
第2問 ①この図形は、転がり(ません)。では、2つめのヒントは、②底の形は、(長方形)。
これだけでは、分からないな。A、B、Cのどれかだと思うけど……。
分かった! 底の形が長方形はBだ!
でも、Cだって底の形は長方形だよ。この2ヒントでは、答えが出せません!
この2ヒントでは、正しい図形を見付けることができないのですね。それでは、この2ヒントのどこを直したら、答えることができるでしょうか?
学習のねらい
2ヒントのどこを直したらいいだろう?
見通し
2ヒントの中でおかしいヒントはどこでしょうか?
2番目じゃない? 底の形が、長方形だから分からないんだよ。
BやCをAのような向きにしてみると……?
自力解決の様子
A つまずいている子
BやCの「立体の向きを変える」というアイデアに気付かない。
B 素朴に解いている子
2つめのヒントを「面の中に長方形以外の形があります」としている。
C ねらい通り解いている子
立体の向きを変えて、底面を三角形や五角形にすることに気付き、ヒントも修正できる。
学び合いの計画
自力解決を3分ほど設定した後、3~4人程度のグループで交流させます。そこで自分の考えや困り感を共有します。
イラスト/横井智美
『教育技術 小五小六』 2022年2/3月号より