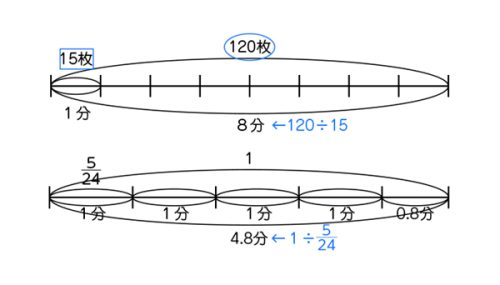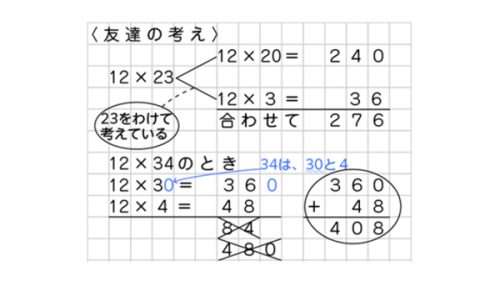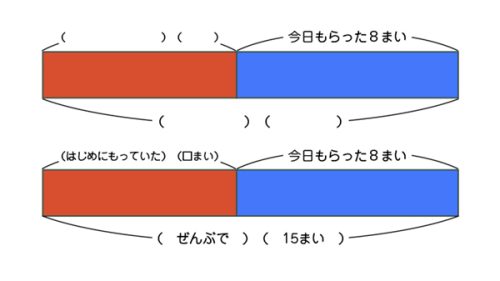小1算数「なかまあつめ」指導アイデア(3/4時)《どちらがおおいかしらべよう》
執筆/福岡教育大学附属久留米小学校教諭・廣木 伸
編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準
(本時の位置 3/4)
本時のねらい
集合の要素の個数の大小を、おはじきなどの媒介物による1対1対応によって判断することができるようにする。
評価規準
おはじきで置き替える1対1対応による数の大小の比べ方を理解し、数の大小を比べることができる。(知識・理解、技能)
問題場面
あそんでいる きつねさんと うさぎさんは、どちらが おおいですか。
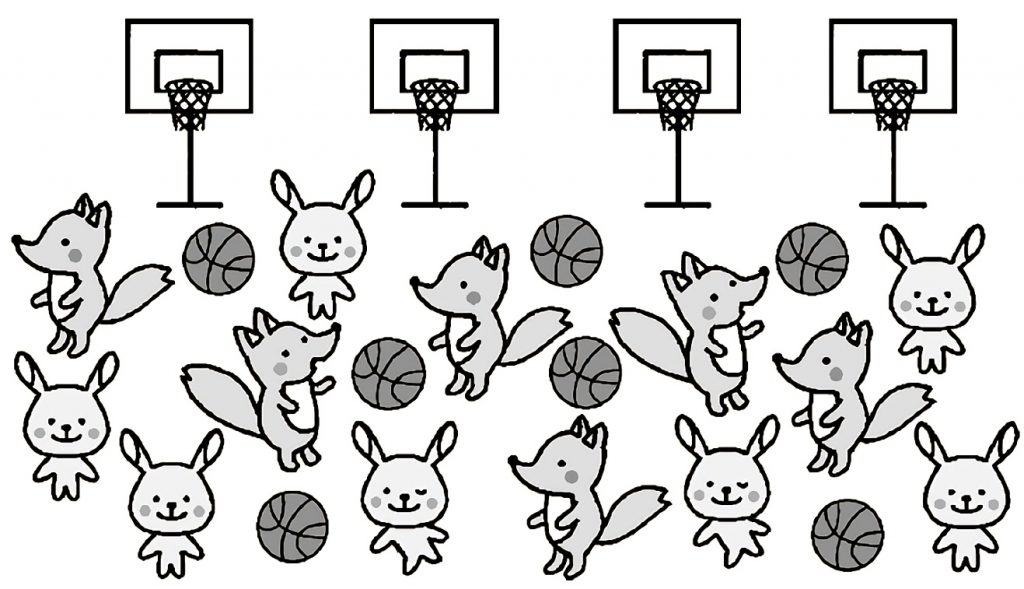
キツネさんとウサギさんは、何をしているのかな?
ボールで遊んでいます。
楽しそうですね。同じ人数で遊んでいるみたいだね。
え? キツネさんが多いよ。
多いのは、ウサギさんじゃないの?
あれ? 同じじゃないの? じゃあ今日は、ウサギさんとキツネさんはどちらが多いのか調べてみましょう。どうすれば、どちらが多いかわかるかな?
本時の学習のねらい
どちらがおおいかしらべよう。
見通し
・線で結ぶ。
・絵カードを動かす。
・おはじきを置いて、並び替える。
前の時間は、どのように比べたかな?
線で結んだよ。
カードを動かしたよ。
今日は、カードを使わないことにします。
でも、線は引きにくそう。
今日は、おはじきを使ってみましょう。
自力解決の様子
A:つまずいている子
・おはじきをきちんと置けない(落ちがあるなど)。
・おはじきを置いた後、どうしてよいかわからない。
B:素朴に解いている子
・おはじきを適当に並べ、比較している。
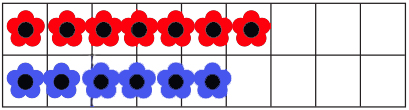
C:ねらい通りに解いている子
・おはじきを上下にそろえて並べ、比較している。
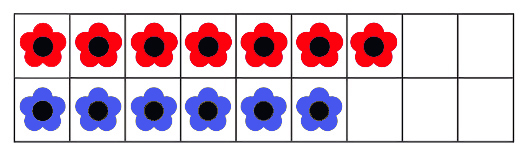
自力解決と学び合いのポイント
イラスト/佐藤雅枝 横井智美
『小一教育技術』2018年4月号より