小6国語「新聞の投書を読み比べよう」指導アイデア

教材名:「新聞の投書を読み比べよう」 東京書籍
指導事項:B書くこと イ・オ C読むこと イ・オ
執筆/新潟大学教育学部附属新潟小学校教諭・中野裕己
編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、新潟県公立小学校教諭・井上幸信
目次
単元で付けたい資質・能力
①身に付けたい資質・能力
本単元では、理由付けの仕方や根拠の挙げ方を工夫して、自分の考えを明確に表現する力を育むことを目指します。本単元で取り組む言語活動は、新聞の投書を書くことです。投書は、ある出来事やテーマ、身近な問題などについて、自分の意見を発信する手段の一つです。
読者は、投書に書かれた内容を基に、その意見に共感できるか否かを考えながら読みます。したがって、読者が自分の意見に納得できるよう、段落一つ一つの内容を工夫して、文章全体を構成する必要があるのです。
②言語活動とその特徴
本単元では、スポーツの取り組み方についての意見を述べた、四つの投書を教材として扱います。これらの投書では、「楽しむこと」「勝利を求めること」という二通りの意見が述べられています。そして、理由付けの仕方や根拠の挙げ方について、それぞれ工夫が施されています。
そこで、この四つの投書を読み比べながら、読者の立場で、納得できる意見について検討をします。この検討を通して、理由付けの仕方や根拠の挙げ方の工夫を捉え、自らが書く投書に生かすことができるようにします。
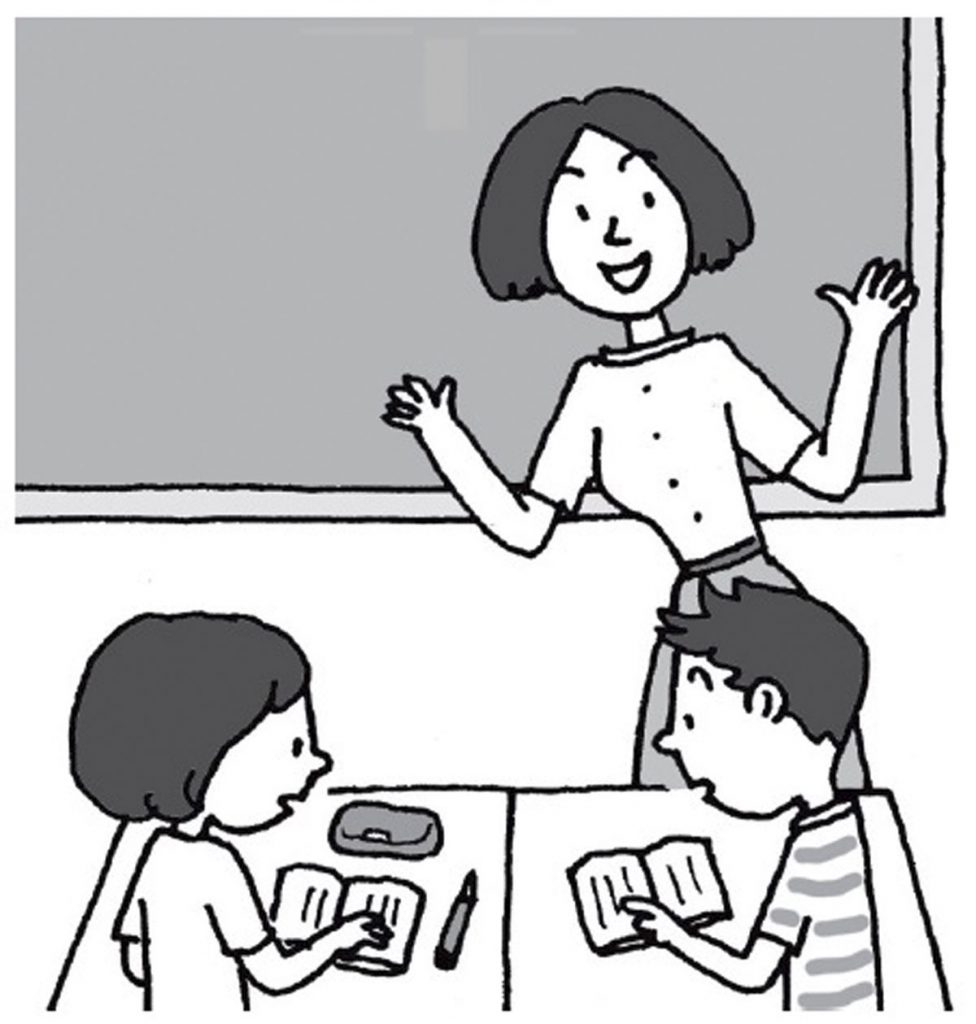
単元の展開(8時間扱い)
主な学習活動
第一次(1~3時)
①実際の新聞に掲載されている投書を読み、投書について知る。
・新聞の購読者層を考えたり、投書の内容を読んだりして、自分の意見を社会に発信するという投書の特徴を理解する。
②投書のテーマを設定し、投書(第一稿)を書く。
・日々の生活で感じていること、総合的な学習の時間や道徳で学んだことを出し合って、それぞれテーマを設定する。
③書き上げた投書(第一稿)と教科書に掲載されている投書①とを比較して、感じたことを出し合う。
→アイデア1
・子供の発言を価値付けて、投書の書き方に課題意識をもてるようにして、学習課題を設定する。
【学習課題】読んだ人が納得する投書を書こう。
第二次(4~6時)
④教科書に掲載されている投書①~④を読んで、テーマ(スポーツの取り組み方)について自分の考えをもつ。
⑤「楽しむこと」と「勝利を求めること」のどちらに納得したか、交流する。
→アイデア2
・なぜ納得したのかを問い、理由付けの仕方や根拠の挙げ方の工夫が、子供の言葉で語られるようにする。
⑥前時を振り返り、「読み手を納得させる工夫」をまとめる。
・前時の子供の発言を抽出して提示することで、「読み手を納得させる工夫」に気付けるようにする。
第三次(7~8時)
⑦二次で学んだ「読み手を納得させる工夫」を観点として、投書(第一稿)を推敲する。
→アイデア3
⑧投書(最終稿)を書く。
アイデア1 自分の投書と教科書の投書①を比べて、課題意識をもつ

子供は、それぞれテーマを設定して投書(第一稿)を書き上げています。ここでは、教科書の投書①をモデルとして提示し、自分の投書と比較することを促します。
子供は既に投書を書いているため、テーマの設定、文章全体の構成、段落の内容といった、投書の書き方を意識して発言します。
野球を、テーマにしているね。
イラスト/畠山きょうこ 横井智美
『教育技術 小五小六』2019年6月号より

