問いを生み出す「質問力」の育て方〈第1回〉コミュニケーションに不可欠な3種類の問いとは?
生成AIが普及していくこれからの時代では、「何を問うか」という力がますます重要になってきます。しかし、そもそも「問いの立て方」を十分に学ぶ機会がなかった私たちにとって、「問うことを教えること」は容易なことではありません。この記事では、神戸大学附属小学校教諭の友永達也先生が、子供の「問いを生み出す力」を育むための指導理論を解説します。対話を活発にし、思考を深めるために不可欠な「3種類の問い」とは何か? 問いの重要性を知るだけでなく、具体的な指導法までわかる、教育関係者注目のシリーズ第1回です。
執筆/神戸大学附属小学校教諭・友永達也

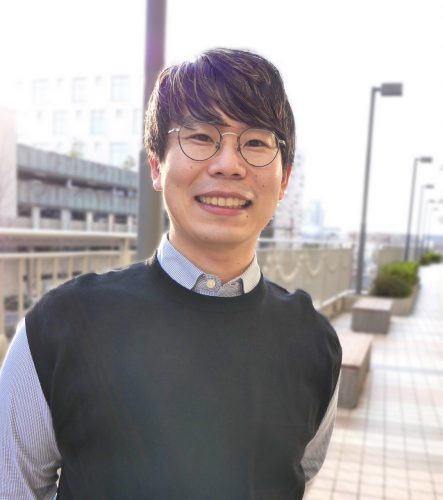
執筆/友永達也(ともなが たつや)
神戸大学附属小学校教諭。専門科目は国語科。とくに話すこと・聞くことの指導に関心があり、現在、学習者が問う力を高めるカリキュラムの開発や、メタ認知に基づく判断を生かしたコミュニケーション教育、小学生を対象とした聞き書きプロジェクト等に取り組んでいる。また、国語科を中心として、問題解決的な単元デザインや、それを支えるノート指導にも日々取り組む。 全国大学国語教育学会、日本国語教育学会、日本教育方法学会、国語教育実践理論研究会(KZR)に所属するとともに、尼崎市の国語科授業サークルのアドバイザーを務めるなど複数の国語科研究会の運営にも携わる。
単著に『対話を深め・問う力が育つ 質問力アクティビティ40』(東洋館出版社・2025年)、『1回10分!トークタイムできく力を育てる ストラテジック・リスニング』(明治図書・2020年)が、分担執筆に『対話的に学び「きく」力が育つ国語の授業』(明治図書・2018年)、『「感性的思考」と「論理的思考」を生かした「ことばを磨き考え合う」授業づくり』(明治図書・2020年)がある。
目次
なぜいま問うことが重要なのか
生成AIの登場によって、現代はかつてないほど人類に問うことが求められている時代と言えるでしょう。プロンプト(指示文)を問いかけとして生成AIに入力すれば、その問いに対する答えがすぐに(そして大量に)表出されます。このような時代では、答えを獲得したり暗記したりすることの意味は薄れます。しかしその一方で、いかに問うかということが重要となってきます。適切な問いを生み出すことができれば、自分にとって必要な情報を得ることができるからです。
本記事では、そんな「問いを生み出す力」をどうすれば子供たちに育むことができるのかという指導理論について、具体的な実践アイデアも交えながら紹介します。よりたくさんの指導アイデア、より詳しい理論的な説明が知りたい方は、筆者が2025年に刊行した『対話を深め・問う力が育つ 質問力アクティビティ40』(東洋館出版)をぜひ手に取っていただけると幸いです。
問うことを指導するのは難しい!
そもそも問いを生み出すことは、簡単ではありません。なぜならば私たちは、「いかに答えるか」ということに比べて、「いかに問うか」ということを十分に学んできていないからです。そして大人たちがそうであるならば、次世代を担う子供たちに問う力を授けることも、また難しいと言えるでしょう。
もう一つ、問いを生み出すことが難しい理由があります。それは、コミュニケーションの中で質問をしようとすると、目的やお互いの立場、やり取りの展開が目まぐるしく変化するために、瞬時の判断が求められることになるからです。対話のなかで「○○について質問してみよう」と思っても、そう決心したときには話題が別のものへ移ってしまっている(そのために質問できずに終わる)ということは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。
このように、問うことが社会的にも重要になっている反面で、問うことの指導はそう簡単に実行できることではないのです。では、私たち教師はどうすれば子供たちの「問う力」を育てることができるのでしょうか?
「問い」を生み出す力を育てるには
まずここで重要な用語を確認したいと思います。それは「問う」という言葉についてです。
最近、「物語における読み手の問いを大切にした授業」「子供の問いから始まる学び」といったように「問い」というワードをよく見かけます。本記事においても「問い」ということを扱いますが、大きく分けてこの「問い」には2種類あります。
まずひとつは、「物語における読み手の問いを大切にした授業」でいわれるような探究の軸となるような「問い」です。ここでの「問い」は、問題追究のテーマともなるようなもので、固定的です。そうでなければ追究するテーマがころころと変わってしまい、子供たちの探究もまとまりのないものとなってしまうでしょう。
一方、本記事で焦点を当てるのはコミュニケーションにおける「問い」であり、「質問」とも呼ばれるものです(両者は厳密には区別して考えるほうが望ましいですが、紙幅の都合もあり、あえてここでは両者を区別することは避けておきます)。この「問い(質問)」は、非常に流動的です。コミュニケーションの中で瞬間的に生み出され、時には解決されることなく消えていきます。ですが、言葉のやり取りの中では確かに私たちはたくさんの「問い(質問)」を用いています。とくに幼児期の子供を見ると、大人が困ってしまうほどにたくさん問いを投げかけてくれます(あの問いは成長するとどこにいってしまうのでしょうか)。
もちろん探究の軸となるような問いも、コミュニケーションにおける問いの延長線上にあります。ですから、子供たちの日々のやり取りを支える「問いを生み出す力」を育てることが、学びの探究者としての子供を育てるうえでも有効なのです。
問いがないやりとり/問いがあるやりとり
問いの効果と重要性を示す例として、物語「ごんぎつね」の最終場面で、考えを交流している子供たちの二つのやり取りを比較してみましょう。
➀問いがないやり取り
| 子供A | ごんは最後の場面で悲しかったと思うな。 |
| 子供B | ぼくも! |
| 子供C | わたしはうれしかったんだと思うよ。 |
| 子供D | そうなんだ~。 |
➁問いがあるやり取り
| 子供A | ごんは最後の場面で悲しかったと思うな。 |
| 子供B | なんで? |
| 子供A | だって結局ひとりぼっちの小ぎつねになっちゃったもん。 |
| 子供C | でも、兵十がわかってくれたんだからひとりぼっちじゃないと思うよ? |
| 子供D | じゃあBちゃんはごんはどんな気持ちだと思ってるの? |
問いがあるのとないのとでは、言葉のやり取りの躍動感が違います。➁では、各々が問いを出し合い、それに応答しながら、互いの考えが絡み合ってコミュニケーションが展開されています。おそらくこの後も、最終場面のごんの心情をめぐるやり取りが熱く展開されることでしょう。その対話を支えているのは紛れもなく「問い」だと言えます。一方で、問いのない①のようなやり取りは、お互いが考えを述べておしまいです。誰かの考えに触発されて、新たに考えが広がったり深まったりすることは期待できないでしょう。
このように比較してみると、子供たちは、お互いに広がり深まり合うやり取りにおいて、実に効果的に問いを発していることがわかると思います。

