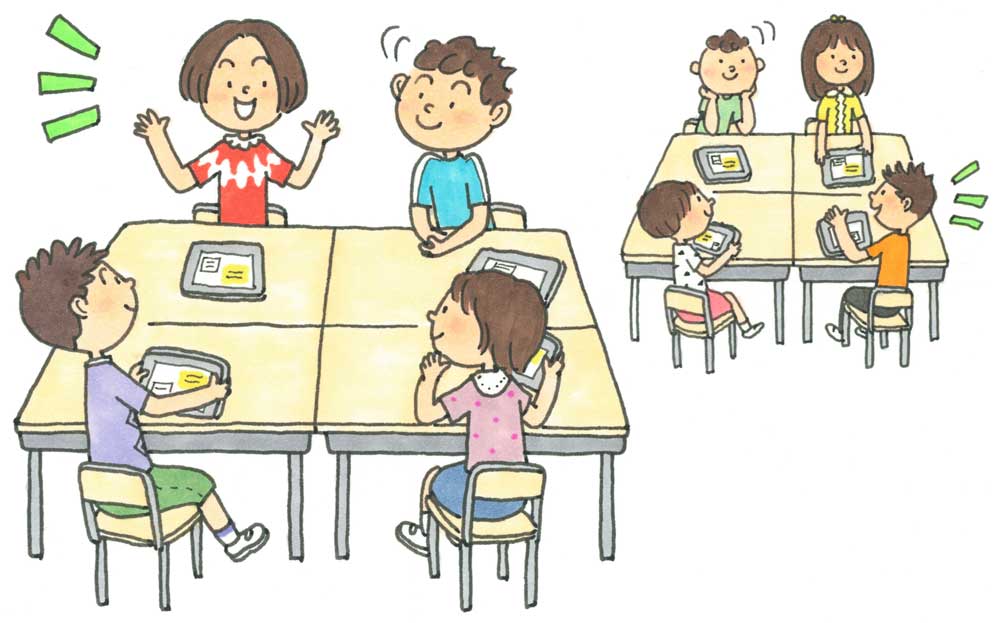【特別支援教育】学級経営②「学級内での人間関係づくり」指導のポイントとアイデア
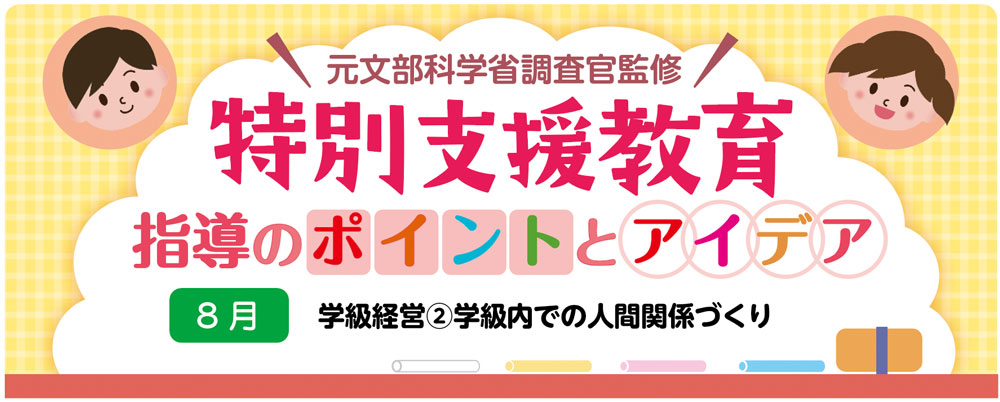
元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈学級経営②「学級内での人間関係づくり」〉を紹介します。子供同士が互いに認め合い、許容し合うことができるような学級づくりの手立ての具体的な例をお届けします。温かい雰囲気の学級づくりのヒントにしてください。
執筆/熊本市教育委員会事務局学校教育部教職員課指導主事・美坂昌宏
監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子
白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授・山中ともえ
目次
特別支援教育 年間執筆計画
04月 児童理解①児童の状態の把握
05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用
06月 児童理解③児童への具体的な対応
07月 学級経営①多様性を尊重する学級
08月 学級経営②学級内での人間関係づくり
09月 学級経営③多様性を尊重する学級
10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業
11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫
12月 授業づくり③ICTの活用
01月 連携①保護者との関係づくり
02月 連携②校内連携
03月 連携③関係機関の活用
【解説編】学級内での人間関係づくり
学級内での人間関係づくりは、学級経営の基本であり、特別支援教育を推進するにあたっても大切なものです。子供同士が互いを認め合い受容し合うことができるような人間関係を温かい雰囲気のもとにつくっていくことが大切です。
1 対話的な活動で互いを認め合い受容し合う支持的風土を醸成する
2022年12月公表の文部科学省による全国調査では、小中学校において「学習面又は行動面で著しい困難」を示す児童生徒数の割合が推定値8.8%であることが明らかにされました。「学習面又は行動面での著しい困難」とは、子供だけに原因があるだけではなく、授業のあり方や学校内の環境も大きく影響しています。また、この数値は、教師が支援を必要としている子供と接するなかで、「学習で困っている子供にどのように指導したらよいか分からない」「生活のなかで友達とうまく関わることができない子供に、どのようにアプローチしたらよいのだろうか」など、教師の悩みの割合とも考えることができます。
これらの課題を解決するためには、子供同士が互いのことをよく知り、認め合い、受容し合う支持的風土を醸成していくことが大切であり、その取組の1つとして、「対話的な活動」を取り入れることが効果的です。
2 話すことがわくわくするテーマで楽しい対話の時間をつくる
これまで学級担任として取り組んできた、10〜15分程度でできる楽しい対話的な活動を紹介します。
まず、3〜4人の少人数グループをつくります。次に、対話のテーマを決めます。テーマは、子供たちが「聞きたい」「話したい」と思うようなものにします。例えば、「ドラえもんの道具で一番使ってみたいものは?」「朝ごはんは、パンが好き? ご飯が好き?」などです。子供たちがこれらのテーマを聞いて、思わず「自分だったら〇〇だと思うな」「友達はどんな考えなんだろう」と思うようなわくわくするテーマが効果的です。
テーマの発表後、子供たちは3分間で自分の考えをまとめます。このときに、ノートやタブレット、PCなどに記入するようにします。わくわくするテーマに加えて、事前に考えをまとめる時間を確保することで、誰もが安心して活動できる環境を整えます。その後、話す順番を決めて、1人ずつテーマに沿って話していきます。時間は全員で4分間程度です。聞いている人は、相手の顔を見て聞いたりうなずいたりしながら聞くように声かけをします。
3 対話の「振り返り」で教師の「感動」を伝える
教師は、対話中に子供たちの様子をよく観察しておきます。例えば、相手の顔を見て話をしている子供やうなずきながら聞いている子供、友達が話し終わった後に「いいね〜」「それ分かる」などの反応を返しているグループ、拍手をしているグループなどです。なかには、自分の考えを話すことができずに困っている子供もいるかもしれません。そのようなときに温かく話し始めるのを待ったり、別の子が代わりに話そうとしたりしている様子などにも注目するようにします。これらの様子を動画として記録しておくのも有効です。
対話が終わった後は、最も大切な「振り返り」の時間です。振り返りでは、子供たちの話し方や聞き方でよかったところを振り返ります。最初のうちは、教師が子供たちの対話の様子を見ていてよかったと思うところを紹介していきます。また、対話中の子供たちの様子を動画で一緒に見ながら、感動を伝えていくのも効果的です。「うなずきながら話を聞いていて、先生もうれしくなった」「笑顔で相手の考えを聞いていて、先生も幸せな気持ちになった」など、教師の「感動」を伝えていきます。このような教師の温かい眼差しによって、子供たちは相手との関わり方に自信をもち、よりよい人間関係を構築していく力を少しずつ獲得していきます。そして、子供同士でも振り返りを行い、考えや感動を伝え合いながら、互いを認め合い受容し合うようにすることも大切です。
4 いじめを起こさせない学級にするために
いじめが起きる原因は様々ですが、学級内の価値観が限定的であったり、教師や子供のコミュニケーションが不足していたりすることなどがいじめを起こす要因の1つでもあると考えられます。よりよい人間関係を築いている学級は、いじめが起きにくい学級であるとも言えます。子供が互いを認め合い受容し合い、多様性を尊重できる学級をつくることが、いじめを防ぐとともに、インクルーシブな学級へと成長していくことにつながると思います。