小六国語「幸せになるためのリフレクション」の成立条件とは

凄腕実践者・山田洋一先生が、「子供自身のリフレクション」により深い学びが生まれる条件について考察。さらに、国語の授業実践例の中で、実際に機能させるための様々な工夫や仕掛けを具体的に提案します。
執筆/北海道公立小学校・山田洋一
1969年北海道札幌市生まれ。北海道教育大学旭川校卒。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。著書は『気づいたら「忙しい」と言わなくなる教師のまるごと仕事術』(黎明書房)ほか多数。
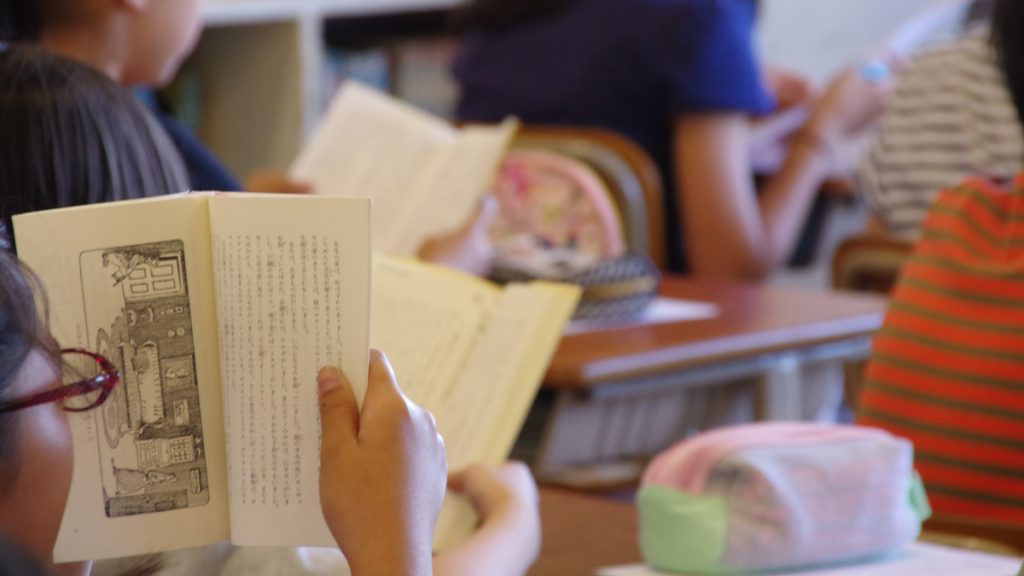
目次
深い学びを促すための子供自身のリフレクション
実際の教室を見れば、学習本体に時間が大幅にかかり、時間が足りない。そんな中、教師たちはリフレクションをかなり無理して行っています。なぜ、無理してまで行っているのでしょう。それはリフレクションの意義を十分に理解しているからでしょうか。残念ながら違うようです。
最近の教育思潮が、リフレクションをするように奨めていて、「なんとなくやるとよいらしい」という程度の納得で、子供たちにリフレクションをさせている場合が多いようです。その程度の意識で行っているうちは、リフレクションが効果を生むことはほとんどありません。
リフレクションをやる暇があるなら、新出漢字を一つでも多く教えた方がよいというのが、多くの現場教師の本音でしょう。しかし、それでもなお、私はリフレクションを指導に埋め込むことを奨めます。
それは、リフレクションを通して、自分がなりたい学習者像に、どれだけ近づけているかを子供たちに自覚させることができるからです。
自分が成功したり、あるいは失敗を乗り越えたりするなどの試行錯誤をして、「なりたい自分」になっていけることを自覚することは、子供の自尊感情を高めることになります。簡単に言えば、「私もなかなかやるじゃないか」「私もやればできる」という感情を持たせ、自分が有能であることに気付かせることが、リフレクションの本質であり、可能性でもあるということです。
そのことは、最終的に「どう幸せになるか」を子供に身に付けさせることになるでしょう。
リフレクションにおいて、子供たちは、学習が成功した時は「なぜ、成功したのか」を考え、うまくいかない時には「なぜうまくいかないのか」、また「どうすればうまくいくのか」を考えます。これは、人生において「どう幸せになるか」を追求することとまったく同じです。「うまくいったこと」を続け、うまくいかなかったことを改善することが、「幸せになる方法」だからです。そうです、リフレクションを指導することは、「幸せになる方法」を教えることと同じなのです。
では、そうした「幸せになる方法」に気付けるリフレクションとは、どのような過程で行われるリフレクションなのでしょうか。私は、次の6段階で考えています。
①描写
②感情
③評価・価値
④分析
⑤総合
⑥行動計画
リフレクションを成立させる素材研究
前節で書いた6段階を学習過程の中に埋め込むことが、深い学びを生むことにつながります。しかし当然ながら、埋め込むだけで子供たちが有意義なリフレクションができるわけではありません。
そこには教師の授業づくりの質の問題があります。質の問題とは、次のようなことです。友人と映画を見に行ったとしましょう。そして、その帰りに食事をする。よい映画を見た後なら、二人とも調子よく映画について話をするでしょう。互いに気付かなかった点についても交流でき、そこには豊かな時間が生まれます。
しかし、その逆ならばどうでしょう。
二人は、「いやあ、ひどかったねえ・・・」と言って押し黙ってしまうでしょう。ひどい授業の後のリフレクションは、これに似ています。
子供たちに意味のあるリフレクションをさせたければ、リフレクションをしたくなる授業をつくることが、まず大事だと言うことです。
国語授業の達人、野口芳宏先生は、授業づくりに
①素材研究
②教材研究
③指導法研究
という3段階があると主張しています。私は、この3段階の中でも、素材研究の重要性をここで強調します。
たしかに、昨今の忙しい学校を見れば、最も時間をかけられないのがこの素材研究だと言えるでしょう。しかし、子供たちにとって意味のある授業をするためには、素材研究をすることこそが、遠回りのようでいて、実は近道です。なぜなら、素材研究をすることによって、教材研究(何を教えるか)、指導法研究(どう教えるか)の大方が見えてくるからです。
では、この「素材研究」の方法を、光村図書『国語 六 創造』所収の立松和平『海の命』を例にして紹介します。
私が素材を解釈する時に、はじめにすることは中心人物の確定です。中心人物とは、「主題に関わって、ある種の課題を持っていて、その課題を解決、あるいは昇華している人物」と考えています。『海の命』では、太一ということでよいでしょう。次にすることは、中心人物の課題の確定です。この素材では、「ぼくは漁師になる。おとうといっしょに海に出るんだ。」とあるところから次の二つだと考えます。
・漁師になる。
・おとうと一緒に漁に出る。
この二つは、太一が成長することや父が亡くなったことにより「一人前の漁師になる」「(おとうと一緒に漁に出ることはできないので)クエを仕留める」ことへと変質していきます。
次に、これらの中心人物の課題がどう解決されたかを読み取ります。そうすると、前者も、後者も「おとう、ここにおられたのですか。また会いに来ますから。」という太一の言葉によって、解決されていることが分かります。「クエを仕留めることによって一人前の漁師になる」ということに、当初こだわっていた太一は、クエを「おとう」をも含む大きな「海の命」と捉えることによって、当初の課題を昇華し、「解決」します。
このようにクエを見ることによって、「一人前の漁師」になれ、「おとう」と肩を並べる存在にもなれたと考えられます。このように読み取ることで、「めぐみ」の意味、「村一番の漁師」と「一人前の漁師」の違い、「海に帰っていった」、「母の悲しみも背負う」、「海の命は全く変わらない」、最終行の「もちろん」の意味も立ち上がってきます。
このようにして、教師自身が素材と格闘して見えてきた部分こそが、授業において「教えるべきこと」です。つまり、教師自身が素材研究によって、深い学びを体現しない限り、子供の深い学びを生むことはできず、深いリフレクションもさせられないということです。

