小1算数「たしざん」指導アイデア(1/10時)《和が10より大きい数になるたし算》
執筆/東京都公立小学校指導教諭・大村英視
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊
目次
本時のねらいと評価規準(本時1/10時)
ねらい
1位数同士のくり上がりのあるたし算の計算のしかたを考える。
評価規準
和が10より大きい数になるたし算について、計算のしかたを考え、操作や図などによって説明している。
もんだい ドッジボールを している こどもが 9にん います。なわとびを している こどもが 4にん います。こどもは みんなで なんにんですか。
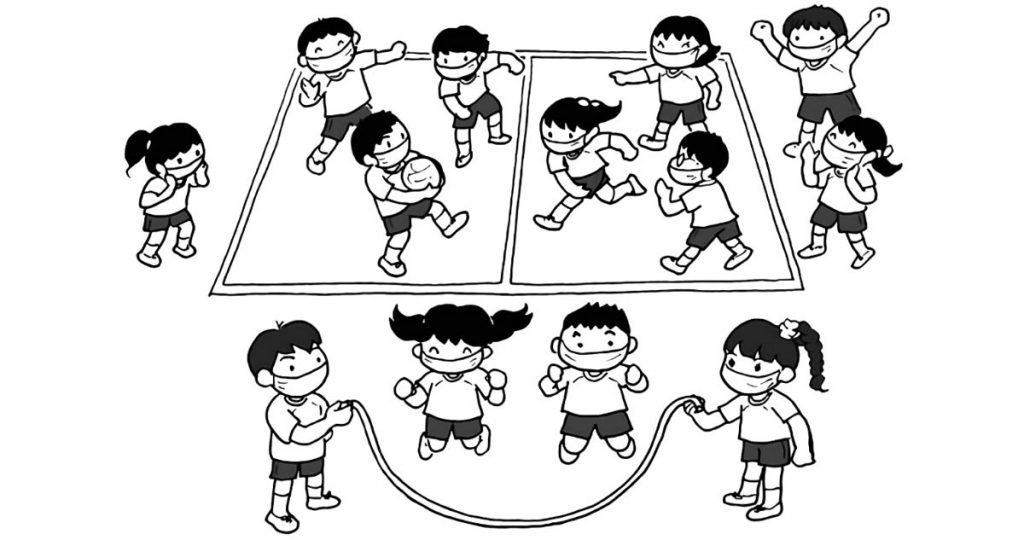
(問題場面のイラストを提示し、休み時間に遊んでいる様子を想起させながら、子供とともに問題をつくっていく)
校庭で子供たちが遊んでいますね。どんな遊びをしていますか。
9人の子がドッジボールをしています。
4人はなわとびをしています。
では、問題です。ドッジボールをしている子供となわとびをしている子供を合わせると、みんなで何人になるでしょう。
分かった!
えー、難しそう。
では、まずどんな式になりますか。
9+4です。
ドッジボールをしている子となわとびをしている子を合わせるから9+4です。
では、みんなで何人いますか。
答えが10より大きくなりそうです。難しいな。
学習のねらい
9+4の けいさんの しかたを かんがえよう。
見通し
9+4の計算のしかたは何を使えば説明できそうですか。
ブロックを使って説明します。
ノートに図を描けば、説明できそうです。
式でも説明できます。
自力解決の様子
A 素朴に解いている子
9、10、11、12、13と、数えたしで答えを求める。
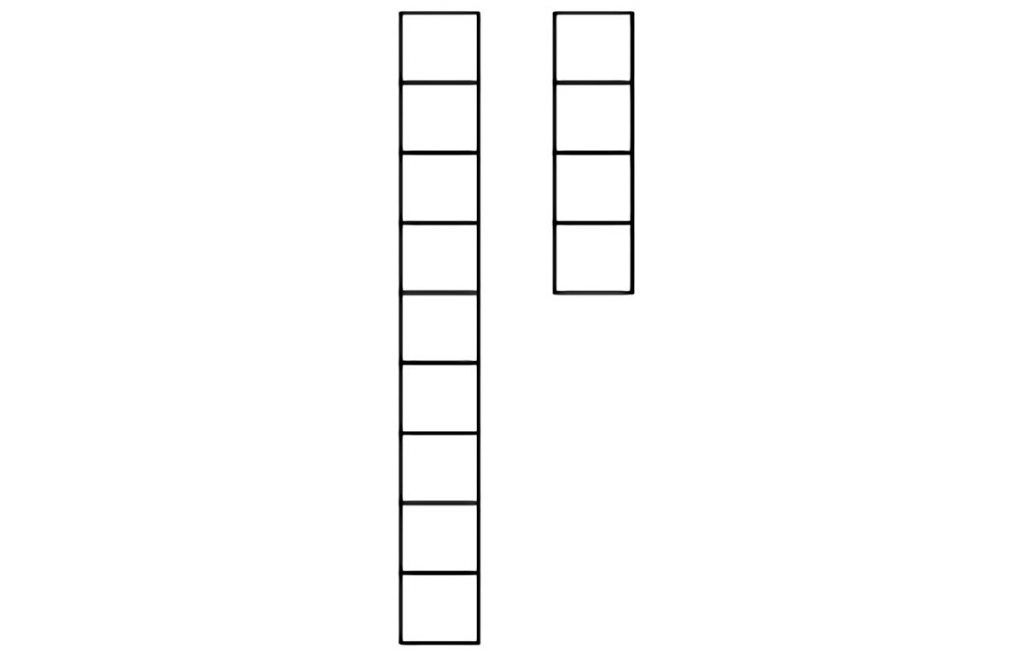
B ねらい通りに解いている子
ブロックや図で、10のまとまりをつくって答えを求め、表現する。
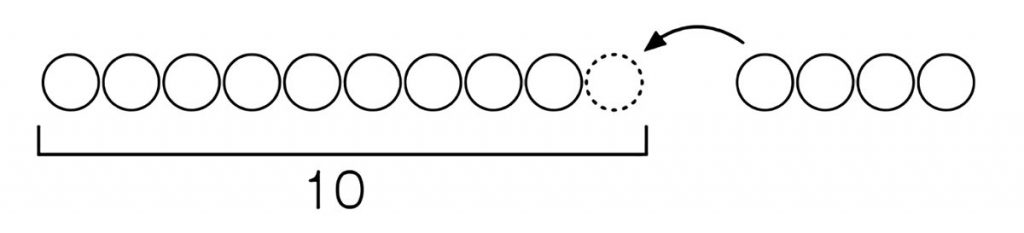
C ねらい通りに解いている子
10のまとまりをつくるために4を1と3に分け、答えを求め、図を用いて表現する。
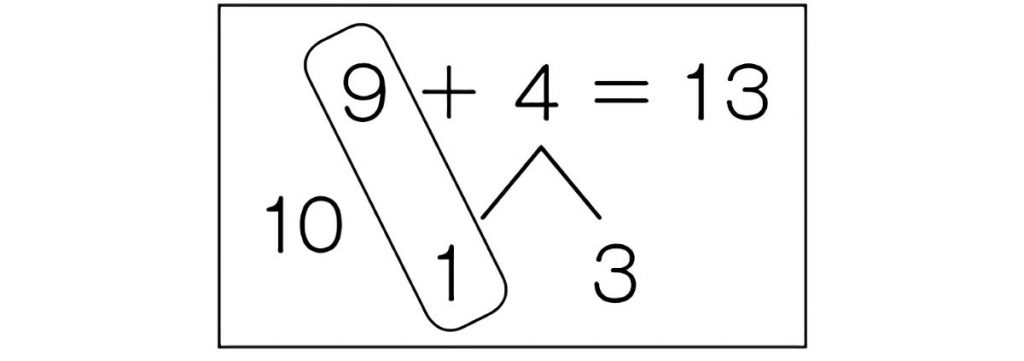
学び合いの計画
イラスト/松島りつこ、横井智美
『教育技術 小一小二』2021年10/11月号より

