小6算数「場合の数」指導アイデア《遊園地の乗り物の順番を調べて、場合の数を考えよう》
執筆/東京都公立小学校教諭・渡辺五大
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊
目次
本時のねらいと評価規準
本時の位置 1/6
ねらい
落ちや重なりがないように調べる方法を考え、説明することができる。
評価規準
図や表に表して順序よく調べることができている。
問題場面 遊園地でまわるコースを考えよう
遊園地の乗り物に一回ずつ乗ります。まわる順番には、どんなものがあるか調べましょう。
・ジェットコースター
・コーヒーカップ
・観覧車
・メリーゴーラウンド

見通し
4種類の乗り物に乗りたいと思います。みんなならどんな順にのるかな。
コーヒーカップ→観覧車→メリーゴーラウンド→ジェットコースター。
ジェットコースター→メリーゴーラウンド→コーヒーカップ→観覧車。
他にもあるかな。
まだまだ、たくさんありそうです。
全部で何通りあるでしょうか。
全部書くのが大変だなぁ。
図にしてみようかな。
落ちや重なりがないように調べよう。
本時の学習のねらい
落ちや重なりがないよう調べる方法を考えよう。
自力解決の様子
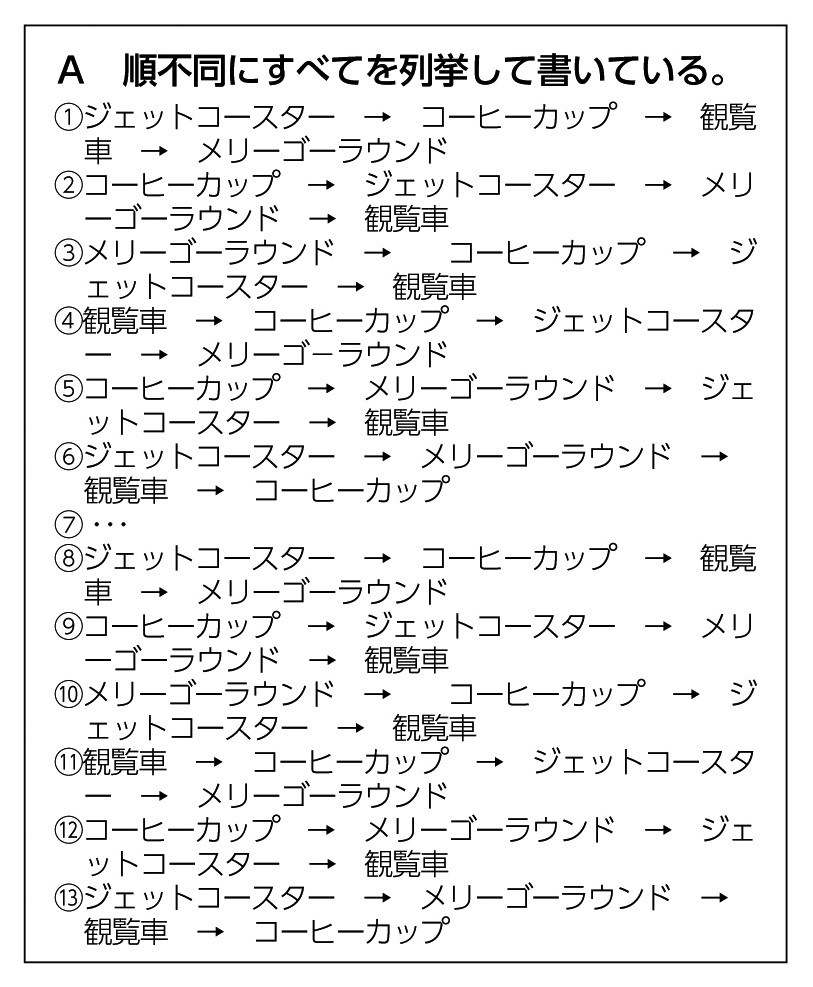
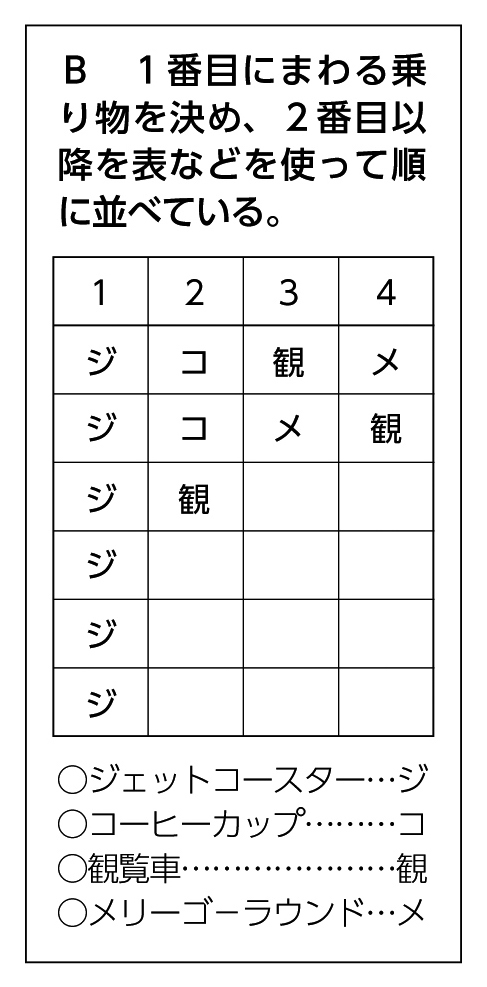
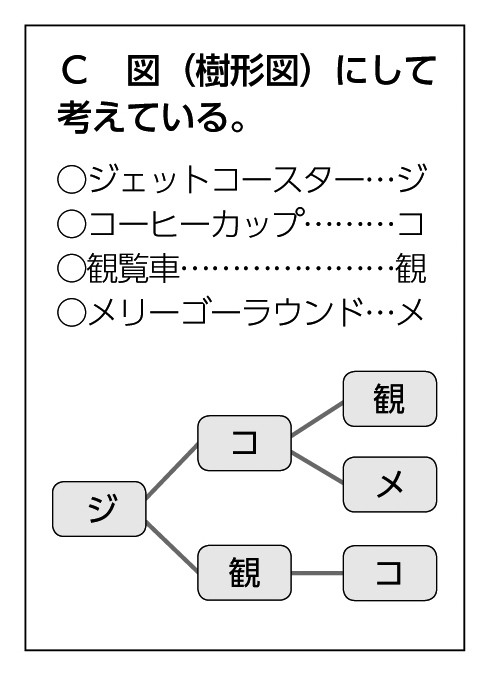
学び合いの計画
イラスト/横井智美
『教育技術 小五小六』2021年1月号より

