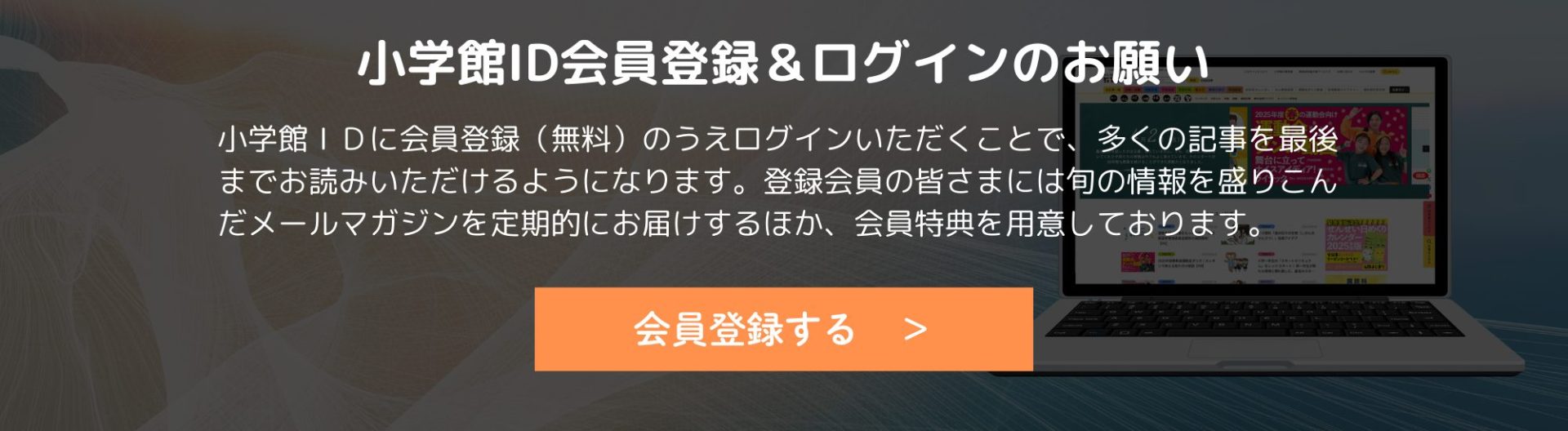指名の仕方に疑問を感じる

子どもたちから質問を募集し、先生の回答とともに紹介する『先生、しつもんです!』。
子どものみなさんはもちろん、大人のみなさんも自分ならどう答えるか、考えて読んでくださいね。
今回の質問は、「指名の仕方に疑問を感じる」です。
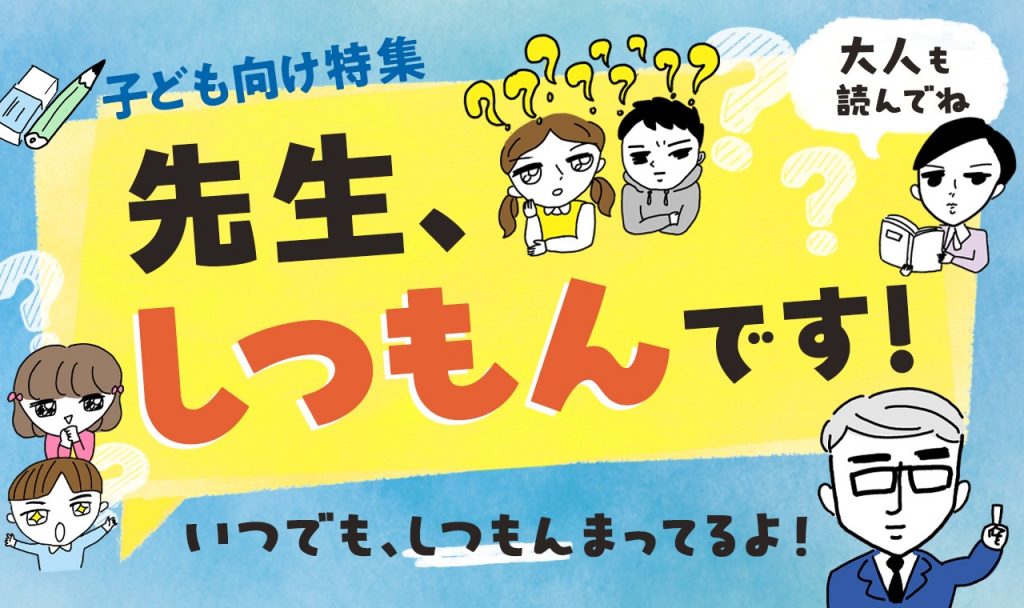
はじめまして。私は数学など理系の科目がとても苦手で毎回憂鬱な気持ちで授業を受けています。
と言うのも、どの授業でも、大問として問われているものに対して解く時間を設けられ、その後ランダムに指名されるという形を、私の通う学校のほとんどの授業が採用しているからです。
まだ得意な科目であればいいのですが、先に書いたように私は「公式を用いて解をもとめるもの」が本当に苦手で、指名されないように影を薄くする毎日です。端から分かっている生徒に当てればよいものを、日付や月、先生の気まぐれで当てられた日にはたまったものではありません。
そこで質問なのですが、なぜ名簿順や「今日は6月25日だから、25番の人」のように指名して解答を言うようにしているのでしょうか。個人の理解度をはかりたいのであれば、定期テストや小テストのようなものでも問題ないように思えますし、指名されても分からなければただ恥をかき、その科目そのものを嫌いになることも、そのままやる気の低下などにつながることがあるのでは無いでしょうか。
また素直に「分かりません」と答えたのに対し「隣の人に教えてもらいなさい」と言われたこともあります。だったら最初から、その科目が得意な生徒のみ指名したらいいのではないのでしょうか。
私の学校がそうなだけかもしれませんが、私は納得がいきません。よろしくお願いします。(ふみつづり・男の子・中学1年生)
#先生しつもんです! #授業のこと
ランダムに指名することで、授業中に集中するきっかけが作られ、すべての生徒が授業に参加する機会を持つことができます
中学生になり、小学校との違いをいくつも感じていることでしょうね。
相談の中で、ほとんどの教科でこのような指名方法が取られていると書かれてありましたが、そうだとすると、学年や学校全体で指名方法を決めているのかもしれません。
ランダムに指名することの利点は、授業中に集中するきっかけを作ることですべての生徒が授業に参加する機会を持つことができる点です。ふみつづりさんの先生は、全員が学習に関与することを促しているのかもしれません。
もちろんテストでも理解度は確認できますが、授業中に指名することで、先生はその場で生徒の理解度を確認し、必要に応じて内容を補足したり、説明を変えたりすることができるので授業の進行中に理解のギャップを埋めることができます。
ふみつづりさんは、数学などの理系が苦手なのですね。苦手な教科の授業で、指名される不安があると授業にも集中できないのではないでしょうか。でも、人間は、食べ物に好き嫌いがあるように、誰にでも得手・不得手があるものです。それを恥と思わなくても大丈夫です。自信を持って「分かりません」と言っていいです。もっと私にも分かるように教えてよ、という思いを持って「分かりません」と言い続けていいです。
分からない生徒はふみつづりさんだけではないと思います。きっと、ふみつづりさんの「分かりません」という発言で、「私も分からない」という声が聞こえてくるかもしれません。その教科が得意な生徒だけで授業を進めてしまっては、苦手な生徒はさらに授業に参加できないままになってしまう可能性があります。いろんな生徒がいて、いろんな考えがあって、苦手な生徒も得意な生徒もいて、それで授業ができていきます。
もしできるなら、これからは「分かりません」と思うときに、どの部分が分からないのかも言えると良いと思います。それが自分の中で分かってくると、少しずつ分かる部分が増えてきますよ。
以前、私のクラスにこんな生徒がいました。テストを返したとき、私のところに来て「先生、私、テストはできないけれど、数学は好きだからね」と言うのです。中学校3年間で学ぶことがたくさん好きになれると一生の財産になりますよ。
(元中学校校長・「全国教育交流会」代表・中野敏治先生)
※募集は終了いたしました。