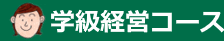|
自主的な活動が増えると、子どもが関わり合う場面が増えてきます。その中で、自分と違う考えの仲間への接し方や役割遂行の在り方などでぶつかることも出てきます。しかし、このような時こそ、さらにより良い集団となるためのステップです。子どもたち同士で問題や課題を解決できるように教師が働きかけることが大切です。
ここで教師は、
子どもたちと⼀緒に活動し、自主的な活動を評価
をすることが重要です。そして、学級生活や活動について振り返り、
みんなでがんばったことを相互に認め合う話合いを通して、満⾜感や充実感を共有し合います
。このような意図的な活動を設定することが大切です。
|